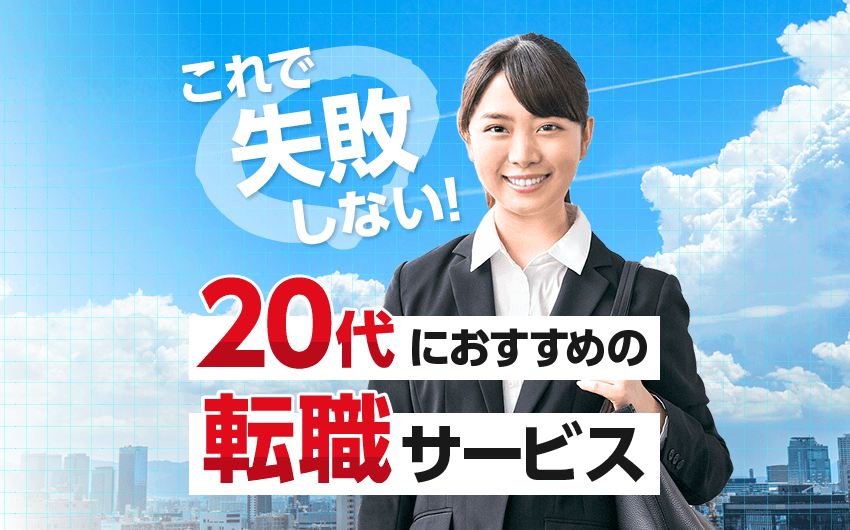目次
キッカケは「子どもたちの笑顔を守るため」
――2006年に設立され、現在では全国に支部が作られているファザーリング・ジャパンですが、設立のキッカケはなんでしょうか。
当時、お父さんが子育てしている様子はほとんどみかけませんでした。
僕は13年前から保育園への子どもの送迎をしていますが、当時、送迎にお父さんがやってくることは皆無でほぼすべての送迎はお母さんが対応されていました。それがどういうことか。
お母さんは保育園に子どもを預けてから仕事をし、仕事を切り上げて迎えに来て、家では食事をつくっていたということです。
この大変さは、やった人にしかわかりませんがとてつもなくハードなスケジュールです。
毎日そんな生活をしていては、とてもじゃないけど笑顔ではいられなくなって、子どもとも余裕をもって接することはできません。
それが、子どもの笑顔を奪っていくことに繋がるんですね。余裕をもって子育てをすることはとても大切です。
実際に僕も子育てをしていて感じていることですが、余裕をもって家族が楽しく関われていると、みんなの表情は豊かになり、笑顔も多いと思います。
お父さんお母さんに余裕がないと子どもたちの笑顔を奪うことに繋がってしまいます。
子どもたちの笑顔を守るためにも、お父さんお母さんの子育ての在り方を変えていきたいという思いが法人を立ち上げた経緯です。
「イクボス」でトップの意識が変化しても、現場はどう行動していいか分からない
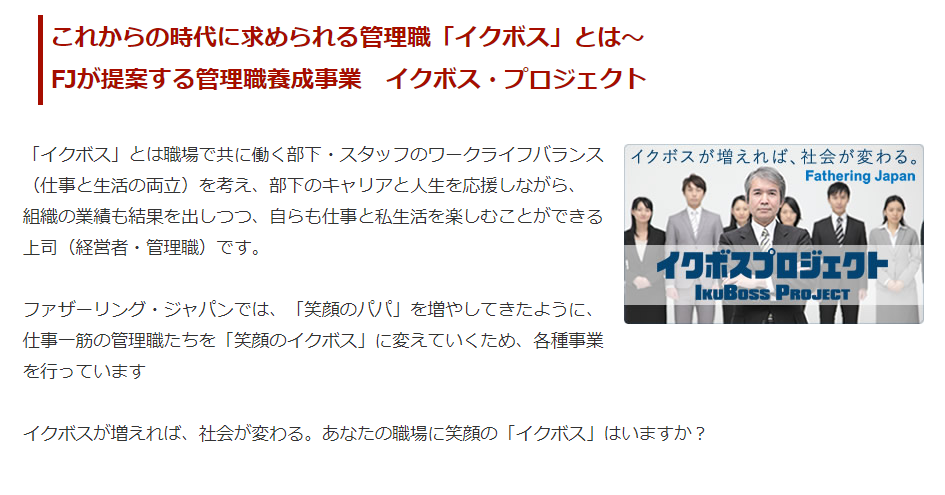
――「イクボス・プロジェクト」発足から現在まで、篠田様から見て企業・自治体の管理職側の働き方に対する意識にどのような変化があったと感じられますか。
現在イクボスの企業同盟というものがあり、そこでの意見交換の中では、管理職の意識そのものは変わっているという実感はあります。
いわゆる組織の中にダイバーシティの概念が必要であるという認知がされてきていることや、「我々の頃は……」という考えが少しずつ薄れてきました。
管理職側の意識の変化という意味では、働き方を改善していくために生き方やキャリアデザインだけではなく、いわゆる「ウェルビーイング」という考え方が理解されつつあるのではないでしょうか。
――上の世代の働き方の考えや雰囲気が、まだまだ下の世代に残っているとも言われていますがいかがでしょうか。
いわゆる昭和のような、夫はバリバリ働いて妻は専業主婦という考えと同じようなものを求めてる雰囲気はまだまだ根強いとは思います。
全体の雰囲気やイメージを個々人で見ると変わってきていると思いますが、まだまだ「男性はこう、女性はこう」というイメージに引っ張られている傾向があります。
――一方で「イクボス宣言」をおこなったにもかかわらず、育休取得率が低いままといった企業や自治体のニュースがありますが、宣言後の実態が伴わない理由として何が課題になっているのでしょうか。
実態が伴わないことのひとつに、トップの発信が、現場のマネージャークラスにまで浸透していないことがあると思います。
会社が男性の育休を推奨していても、部下から育休を取りたいというオーダーがないので、課題意識を感じられず、行動が変わらない。
イクボスが大事と言われても、どう行動していけばいいのかあまりイメージをつけられないというのが現場の多くの認識ではないでしょうか。
トップがメッセージを発信したら、具体的に男性育休100%というメッセージと共にはっきりと行動計画に落とし込むところまで整えて、制度運用を全社員に適用させることでようやく数字が変わってくると思います。
コロナ禍によってワーク・ライフ・バランスがすべてうまくいったわけではない
――昨今のコロナ禍によって、男性のワーク・ライフ・バランスという側面でどのような変化があったと考えられますか。
コロナ禍以前からワーク・ライフ・バランスが大切と言われながら、なんとなく社会の雰囲気や会社に言われて仕事をしないといけないという理由で実現できなかったものが、コロナ禍によってこうも一瞬で実現できてしまったのかと感じるところではあります。
ただ、在宅ワークやリモートワークになり、家にいる時間が増えてもワーク・ライフ・バランスが直ちにうまくいくわけではないと感じます。
色々な方々とお話をすると、目立って聞くのは夫婦でワークスペースの取り合いや、男性側が家にいてもあまり生活スタイルが変わらず、むしろ一緒にいる時間が増えて迷惑というお話も聞くことがありました。
ワーク・ライフ・バランスへの準備ができていなかった家庭は、一緒にいる時間が増えたことで、今までうやむやになっていた家庭のことがすべて浮き彫りになってしまったんじゃないかなと思います。
そういう意味では、以前からワーク・ライフ・バランスに対する準備ができていたかどうかが問われた半年間だったと感じます。
「子育ての軸」を決めることでプレッシャーが解消できる
――仕事と家庭の両立や金銭面など、親になることのプレッシャーは男性側も大きいと思います。こうしたプレッシャーとどのように向き合うべきでしょうか。
まずは子育てをする中でどういうことをするのか、何をしたいのか、どういうことを子どもに提供したいのかをひとつずつ明らかにして、子育ての軸を決めることが大切です。
プレッシャーを感じるということは、「子育てって大丈夫かな……何したらいいのかな」と、子育ての実感が持てず、分からないことが原因です。
金銭面での話も多くの方から聞きますが、子どもにお金をかけてやりたいことっていうのは山ほどあるので、希望するものをなんでもやらせようとしても無理です。
子どものためにさせてあげたいことが勉強なのかスポーツなのか、よりよい人生を送るためにみなさんが必要だと思うことを、無理なくやらせてあげることが大切です。
子どもと向き合って、何を大切にしていきたいのかを一緒に考え、家族で大事にしたいものを親子で共有していくことで、分からないことでのプレッシャーが解消されていくと思います。
「何のための転職なのか」と徹底的に向き合うことが大切
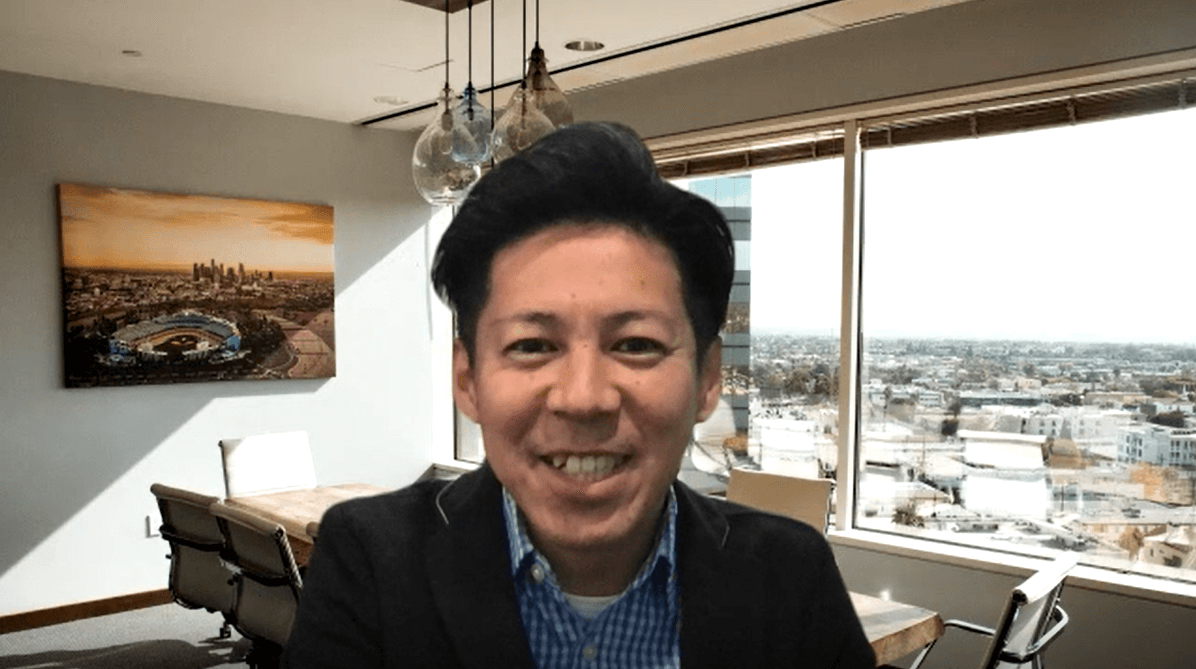
――篠田様の転職の経緯に関する記事を拝見して、実際に家族がいる状態で転職を検討されている男性も多いと思いますが、転職に踏み切る前に必要なことはなんでしょうか。
家族を持ちながら転職に踏み切るにあたってアドバイスできることとすれば、転職の軸とすることが何なのかを理解して、徹底的に考えることが大切なポイントだと思います。
実際に僕の場合、これから働き方や働く会社・職場が多様化していくなかで、自分自身が公務員一択のキャリアで終わるのではなく、子どもたちが就職や転職という人生の迷いどころがやってきたときに、ひとりの先輩としてアドバイスできる状態になっていたいと考えました。
自分がひとつのキャリアしか歩んでいなければ、力のこもったアドバイスができないと思い、色んな生き方があるんだということを伝えるためにも、自分自身の経験が必要だと思ったんです。
僕の場合、転職理由が自分軸ではなかったというのが一番大きいかなと思っています。
だからこそ妻にも公務員を辞めるということに対して同意を得られたのではないでしょうか。
いずれにせよ何のためにこの仕事をしているのか、何のための転職なのかと徹底的に向き合うことが大切だと思います。
自ら率先して職場の雰囲気を変えれば、後々自身の子育ても楽になる
――20代で結婚を控えこれからパパになる方へ、アドバイスをいただけますか。
まず子育て期の仕事と家庭の両立というのは本当に大変で、両立させるには多くの力を借りないと難しいことだと思っています。
子育て期は考える余裕もないくらいに子育てに追われてしまいますし、子育て中心になると限りある選択肢から選んでいくしかない状態になってしまうので、子育て期になってから両立を考えることは非常にリスクのあることなんです。
だからこそ子育て期に突入してから両立を考えるのではなく、結婚したタイミングで「来年子どもが生まれたら再来年にはママが復帰して両立していくだろう」というような先の生活を、夫婦でお互い話し合いをする必要があると思います。
もうひとつは子育てが大変ということははっきりしているので、例えば今の会社や職場内で、結婚して子どもが生まれる前から急なお休みや予定変更がしやすい職場の雰囲気づくりを今から実現することです。
例えば、今すでに子育て中のパパやママが職場の同僚や先輩後輩にいたとして、その人たちに急な予定変更があったときは真っ先に支援を買って出て、「いつ休んでも大丈夫」という環境を作ることができれば、2年後に自分が同じ立場になったとき、気軽に休みを言いやすくなる職場の雰囲気に変えられるでしょう。
子育て中でなくても、ちょっとした家庭の用事で「これで休んでも大丈夫かな」という話が出た時に休める環境を作ることは今からでもできることだと思います。
20代で早くにパパになることを考えている人ほど、こうして今できることを増やしながら自分の休みやすさを作り上げていくことが、後々自分が楽をできる方法になると思います。
――前もって自分から環境作りをすることが大切なんですね。
そうですね。なので結婚や子育てといったことを自分のライフデザインで考えていることがあれば、実際に子育て中の方のお話にもっと触れていただく機会を作ることが大切かなと思います。
男性の育児を社会の雰囲気や制度も含めて当たり前のものにする
――最後に、今後のファザーリング・ジャパンの目標についてお聞かせください。
今は男女で育児をするのが当たり前という意見が多数を占めていながらも、実際にできている状態にはなっていません。
我々NPOとしては、男性の育児というものが当たり前で、100%でなくても気を使うことなくママ同様に育休をとれたり、育児に関わることがママとパパで大きくちがっていることがないという社会の雰囲気や制度が作られ、実現されたと感じた時点で解散できることをこれからも常に意識しながら取り組んでいきます。